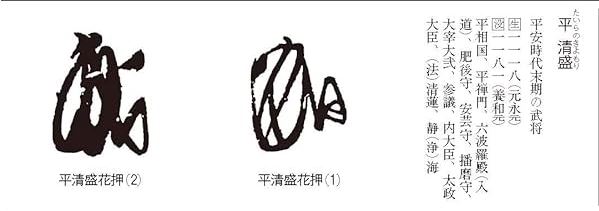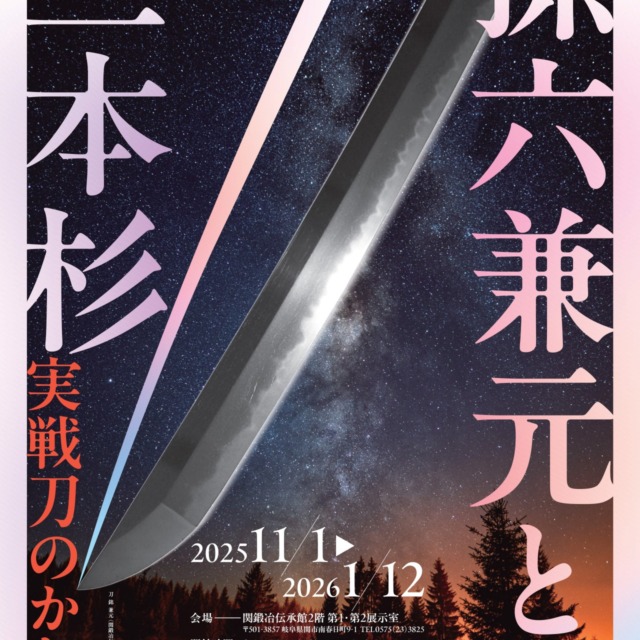令和7年度第3回霜華塾
講師の解説
【鑑定刀1号刀】短刀:銘 長谷部国重
長谷部国重の短刀である。身幅広く、重ね薄く、先反りのついた南北朝期、延文貞治の姿であるが、身幅がここまで薄いのは、長谷部、あるいは三原か青江などがある。
帽子がヤヤ大丸で刃寄りに柾目のところがあるのが国重である。相州伝で身幅が薄く刃紋から初代信国の札があった。長谷部国信という札もあったが国信の場合は大振りのものが多く、この短刀のような長さが尋常のものは少ない。
【鑑定刀2号刀】太刀:佩表銘:加州藤原行光
佩裏年紀:文明十七年二月一日
加州藤原行光の太刀である。この太刀の鑑定は非常に難しい。この太刀は室町初期応永頃の姿をしているが、帽子の焼きが深く返っている。よって時代的に室町初期と合わない。彫物は『八幡大菩薩』と素剣で、これは室町中期から後期にかけて流行ったものであり、帽子の反りが極端に深いのは室町後期である。室町中期の時代は長さ2尺1寸程度が常寸で、この太刀のような長寸のものは1%から2%ぐらいしかない。
従って太刀として注文を受けて作られたものと考えられる。この時代の2尺4寸から2尺5寸のものは通常出来がいい。この太刀の茎を見ると目釘穴2個のうち下の方がオリジナルであり、鏨で開けている。茎尻は加州物独特の片削ぎ中心尻になっている。
藤島の刀は末備前風のところや大和風、美濃風や相州風を加味している。に加州ものの友重の見所は角刃と呼ばれる牛の角のような形の刃で、刃縁に砂流しが掛かる。

【鑑定刀3号刀】
打刀:銘 表銘: 備前國住長舩新拾郎祐定作 金象嵌添文:今泉但馬守四郎左衛門尉高光 宇都宮家大坂詰家老在勤時之所持 裏年紀: 天正十年八月吉日 金象嵌添文 平成三歳末正月九日 本阿弥日洲花押
新拾郎祐定の刀である。この刀は鑑定がそれ程難しくなく、多くの人が当たっていた。長寸で先反りがあり、鎬を盗んでいる。刃紋は複式互の目で末備前の刀である。
刀の長さは、戦国時代永正頃が最も短い片手打ちの刀で、それ以降は長くなり、戦国末期の2尺4寸へ向かう。
【鑑定刀4号刀】脇差:銘 表銘: 作陽幕下士細川主税佐源正義
裏年紀: 天保十二年辛丑八月日
細川正義の脇差である。南北朝期の姿であるが、重ねが厚いので新々刀と考える。大板目肌に渦巻き状の地肌、相州伝ゆえ細川正義あるいは大慶直胤という見方でよい。
切先から茎までを見ると正義特有の二段反りになっている。茎自体は形がO脚になっている。O脚になっていない正義銘の刀は偽物と考える。
【鑑定刀5号刀】打刀:銘 表銘: 於江都藤原清人作之
裏年紀: 慶応三年二月日
齋藤清人の刀である。この刀は当てて欲しい刀である。身幅広く重ね厚く長寸でずっしりと重い新々刀。反りが5分ぐらいでやや浅めの勤王刀で、文久、元治、慶応の姿である。
鎬幅が狭く、切先が伸びて重ねが厚い。特に鎬幅が狭く、板目が流れて沸が強く刃縁に金筋砂流しがあり、帽子が乱れ込んで掃きかけている所が清人である。
【執筆:塾生・川端友二】
彫り物がりました。彫りには優れた彫りもあれば、洗練されていない彫りもあります。違いの説明により、理解力がある方、つまり感性。経験することで感性が磨かれていくのです。
【霜華塾代表:山田】